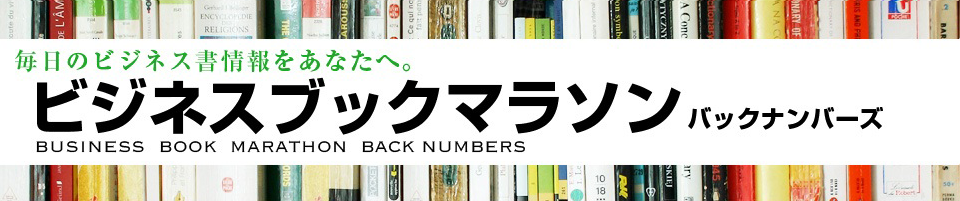【話題!今どきのヒット法則がわかる本】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569860176
本日ご紹介する一冊は、今どきのヒット作品、ヒットコンセプトの理由を、文芸評論家の三宅香帆さんが解説した一冊。
最近は、映画やドラマ、漫画の解釈を解説する「考察記事」「考察動画」が人気で、これらの動画がしばしばヒットのきっかけを作り出しています。
本書では、若者に人気の「考察」文化がなぜ生まれたのか、思想書や文芸作品を引きながらその理由を解説。
文芸評論家の著者らしい、ヒット論、世代論に仕上がっています。
題材として取り上げられているのは、著者が「考察小説」と呼ぶ『変な家』、「考察」の対象になることによりヒットした『鬼滅の刃』、令和のアイドル像を歌ったYOASOBIの『アイドル』、転生モノの代表格である『転生したらスライムだった件』など。
若者たちの根っこにある「報われたい」という思いや、なぜ「正解」が欲しいのか、なぜ「推し」なのか、なぜ転生モノが読みたいのかなど、その行動原理が手に取るようにわかる内容です。
これを読めば、なぜ昭和のおじさんの自己啓発書が売れないのか、現場の先輩のアドバイスが響かないのか、その理由がよくわかりますね。
タイトルからは世代論を思わせますが、実際には、アルゴリズムやプラットフォーム、SNSが変えてしまった人間の行動原理や心理など、技術的な話題にも踏み込んでいます。
なぜひろゆきが若者にウケるのか、なぜひろゆきと陰謀論が結びつきやすいのかという考察も、読み応えがありました。
個人的に一番刺さったのは、
<もはや時代は平成ではない。令和なのだ。批評の時代ではない。考察の時代なのだ>
というフレーズ。
著者によると、考察と批評の違いは以下なのだが、報われることを求める令和においては、「考察」にニーズがあるという。
考察=作者が提示する謎を解くこと
批評=作者も把握していない謎を解くこと
要するに、若者は「正解」が欲しいということだ。
本書を読んでいくと、そのような心理を生み出したのが何なのか、その理由がわかってくる。
では、その次に来るのは何なのか?
そのヒントは、終章「最適化に抗う」でさらりと触れられている。
評論家である著者自身の存在意義すら揺らぐ、現在の若者論。
そこに果敢に挑み、平成との対比を試みた論考は、じつに読み応えがありました。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
2010年以降じわじわと浸透していた、ドラマや漫画、アニメの考察をSNSで楽しむ文化。それが2019年になって--すなわち時代が令和になってから--制作者側が狙ってヒットを生み出すための素地になった
「考察ドラマ」には、3つのプロセスが存在する。ここ重要なところです。
(1)作者(やドラマ制作スタッフ)が、作品に謎とヒントを仕掛ける
(2)視聴者はヒントを見つけ、謎解きの材料にして、シェアする
(3)作品内で、謎解きが行なわれる
なぜ『変な家』は人間の感情や関係性を排除して謎のみを提示できるのか? 答えは回答部分にある。本作は従来のミステリ小説とは違い、伏線を回収するのではなく、読者が自由に考察したのちに、作者が答えを提示する構造となっている
考察=作者が提示する謎を解くこと
批評=作者も把握していない謎を解くこと
正解かどうかわからない個人の解釈を知っても、面白くない。作者が潜ませた”正解”を知ることのほうが、面白い。批評から考察へという流れのなかには、「面白さ」の中身が変わっている様子が見て取れる
令和の若者たちは、物語を楽しむ行為すら「報われること」を目的にしてしまう。だからこそ、正解を当てる達成感が得られる、謎解きや考察ドラマが流行する
萌え=好き(瞬間的)
推し=好き+行動する対象(継続的)
「萌え」は自分と同程度か自分より少し低いところにいる対象に発動する
「推し」は、自分の理想化した行動をとってほしい、その理想化の一部に自分もなりたい対象なのだ
「転生」では「開始で得るスペックが有利なものなら、報われる」という前提に立ち、「ループ」では、「過程で選ぶオプションを間違えなければ、報われる」という前提に立つ
堀江の著作には1を100にする方法が述べられているとすれば、西村の著作はマイナス100を0にする方法を説いている
令和のヒットコンテンツとはもはや、プラットフォームにおいて人びとの欲望が数値として認められたものによってのみ流行するのではないか?
どういうものが数値の結果に出るのか? それは「観る前から報われポイントがわかっている」ものだ
—————————-
『鬼滅の刃』、『変な家』、転生モノ、MBTI…。
令和にヒットする作品や商品、コンセプトの理由がよくわかる内容で、40代以上には、特におすすめの一冊です。
「考察」と「批評」
「萌え」と「推し」
「転生」と「ループ」
「ホリエモン」と「ひろゆき」
のように、対比で解説されているので、平成と令和の違いがはっきり理解できると思います。
ぜひ読んでみてください。
———————————————–
『考察する若者たち』
三宅香帆・著 PHP研究所
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4569860176
<Kindleで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0FZH4RHFD
———————————————–
◆目次◆
まえがき 若者が考察動画を検索する理由
第1章 批評から考察へ
第2章 萌えから推しへ
第3章 ループものから転生ものへ
第4章 自己啓発から陰謀論へ
第5章 やりがいから成長へ
第6章 メディアからプラットフォームへ
第7章 ヒエラルキーから界隈へ
第8章 ググるからジピるへ
第9章 自分らしさから生きづらさへ
終 章 最適化に抗う
あとがき やりたいことや自分だけの感想を見つけるコツ
参考文献 「考察の時代」を理解するための本
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
お知らせはまだありません。