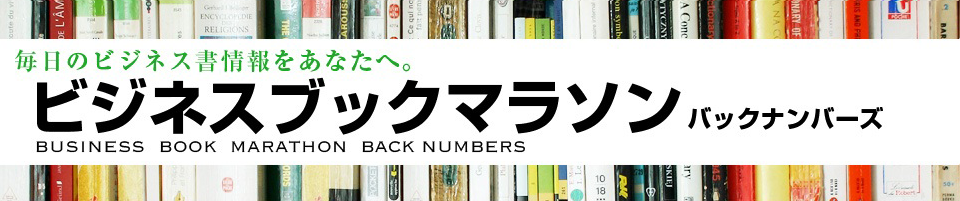【賢く生きるための科学的思考法】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4296000993
本日ご紹介する一冊は、ノーベル賞受賞の天才が考案した、「頭がよくなる科学的思考法」。
著者は、ノーベル賞受賞物理学者でカリフォルニア大学バークレー校物理学教授のソール・パールマッター氏と、同校の哲学教授ジョン・キャンベル氏、そしてスタンフォード大学フリーマン・スポグリ国際研究所シニア・フェローで社会心理学者のロバート・マクーン氏です。
内容的には、科学的な思考法に意思決定論、認知バイアス、哲学の考え方などを織り交ぜて紹介した内容で、さほど目新しさはありませんが、それを発明した偉人たちの歴史が書かれており、押さえておくべき思考・意思決定のツールの概要と起源が、楽しくまとめられています。
個人的に勉強になったのは、シグナルとノイズを見極める際に気をつけたい「どこでも効果」で、知的好奇心旺盛な人、熱心な人ほど陥りやすい罠。
これは、当初の予定より多くの可変要素に目を向けて実験に臨んだ際に、求めているパターンのどれかがランダムノイズによって見つかるという現象です。
これは気をつけようと思いました。
後半はフェルミ推定やら認知バイアスやらの説明がメインで、正直、熱心なビジネス書読者なら大体知っていることがメイン。
読むべきは前半の科学的思考と実験の注意点に関する部分ではないかと思いました。
(こちらはこちらで、科学者なら大体知っている話かもしれませんが…)
特に最近は、ネットを中心に寛容さに欠ける批判が多いと感じますが、複雑な時代には、状況に応じてスマートに意見を翻せる「蓋然的思考」が重要だと思いました。
また、政治やビジネス、投資で誰が信頼に足る専門家かを見極めるためのポイントがいくつも紹介されていて、ビジネスパーソンはぜひ読むべきだと思いました。
ひとつ、ファンドマネジャーに関する部分をご紹介しておきましょう。
<ファンドマネジャーについて詳しく調べていくと、投資するのにふさわしい株式を絶えず的中させているように思えるマネジャーがいずれ見つかるが、それは単に、たくさんのノイズを調べるうちにランダムノイズにパターンを見いだしてしまう現象にすぎない>
本書では他にも、インターネット時代、AI時代にわれわれが詐欺に引っ掛かったり間違った意思決定をしたりする要因に触れており、こちらも注意したいところ。
政治家、ビジネスリーダーは、ぜひ読んでおくべき内容だと思います。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
現実に即した決断を行うにあたって正確な情報が必要になったとき、とりわけ気にかかるのが「自分が使おうと思っている情報源は役に立つか」という点だ
意思決定を行う際には、価値観、倫理観、恐怖感、目的といったものがしばしば重要な要素となる
「インタラクティブな探索」は科学哲学者のイアン・ハッキングによる造語で、人は自分のインプット(貢献)に呼応して何かが変化する様を目の当たりにすると、その実在を強く確信する傾向があるという
明らかになるまでに何世紀、あるいは何千年とかかる現象を扱っていると、自分の集めるデータがその現象の存在と触れ合う一助になっているという感覚はなかなか生まれない
ヒルは「相関の強さ」に加え、「一貫性」も重要な判定基準のひとつにあげている。つまり、検証対象の相関が、別のさまざまな状況でも見受けられるかどうかを確かめるのだ
ヒルはさらに、「時間性」という基準も掲げている。原因が結果に成功することは周知の事実だ。2つの要素のうち、先に生じたものは絶対に結果ではない
相関から因果関係を見いだすときは、相関の強さや多くの異なる状況に適用するかどうかに加えて、2つの要因のあいだに「用量反応」の関係があるかどうかも注目するといい。煙突掃除人を調べて、煤煙の暴露量が多いほど陰嚢がんになる確率が高いと判明すれば、煤煙暴露が陰嚢がんの原因であるとの主張が強化される
蓋然的に考えることには、実感はわきづらいが、科学者にとって大きなメリットがある。信用を失うことなく間違えることが許されるので、間違えたときに体面を保てるのだ
本当のランダムな文字列には、驚くほど長く連続する箇所が意外にいくつもある
目にする情報が増えれば、たとえノイズが増えるだけだとしても、想定外のパターンが見つかる数も増える。そうすると、人はシグナルを見つけたと思い込んでしまう
選挙の投票用紙に候補者の氏名が列記されていて、ほかの条件がすべて同じである場合、最初に書いてある候補者に投票する人の数がわずかに多いという。最初に氏名が記された候補者は、残りの候補者より約5%多く票を勝ち取る
複数の意見を集めることのさまざまなメリットは、互いに意見を出し合ったとたんに台無しになりかねない
—————————-
この本、日本の政治家全員に読んでもらって、感想文を書かせたら、誰が投票するに足る人物か、一発でわかる気がします(笑)。
未来を託すなら、遵法精神がある、約束を守るは当然のこととして、最低限、意思決定に関する知識と、未来を切り拓く姿勢を持っている人にしたいですよね。
ぜひ、読んでみてください。
———————————————–
『アメリカ最高峰大学の人気講義』
ソール・パールマッター、ジョン・キャンベル、ロバート・マクーン・著 花塚恵・訳 日経BP
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4296000993
<Kindleで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0FCS5RSY1
———————————————–
◆目次◆
はじめに 情報に圧倒されやすい時代を賢く生きる思考法
パート1 「現実」を知る
第1章 決断、決断、また決断
第2章 現実と、それを確かめるツールの使い方
第3章 何が何を引き起こすのか
パート2 「不確実性」を理解する
わからないことはわからないと謙虚に受け入れると、本質が見えてくる
第4章 状況に応じてスマートに意見を翻せる人は何が違うのか
第5章 過信と謙虚さ
第6章 ノイズとシグナル
第7章 「そこにないもの」を勝手に見るな
第8章 「少しでもマシなほう」を選ぶために
第9章 「統計的不確かさ」と「系統的不確かさ」
パート3 「為せば成る」という姿勢
第10章 科学的楽観主義
第11章 順序を立てる・概算を出す・上限と下限を決める
パート4 「思考の穴」に落ちないために
第12章 人は意外に経験からは学ばない
第13章 科学にも間違いはある
第14章 「確証バイアス」から逃れるために
パート5 「力を合わせる」
第15章 集団は知恵も狂気ももたらす
第16章 事実と価値を科学的に調和させるには
第17章 討論における課題
第18章 「最先端の科学的思考= 3M思考」に自分をアップデートするために
謝辞
原注
索引
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
同じカテゴリーで売れている書籍(Amazon.co.jp)
お知らせはまだありません。