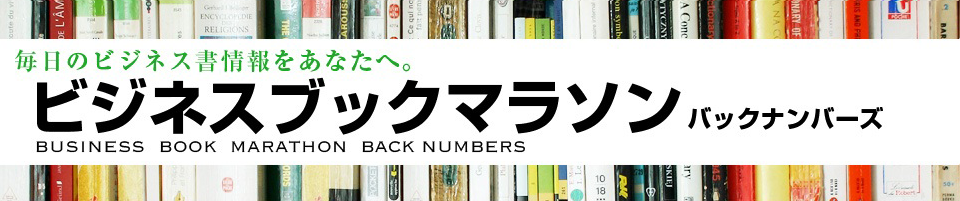【インドのリーダーに影響を与えた権謀術数の書】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4166614851
本日ご紹介する一冊は、古代インドにおける統治の要諦を記した古典、『実利論』を解説した一冊。
『実利論』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4003326318
著者は、在インド、中国、パキスタンの日本大使館で外務省専門調査官として勤務した後、横浜市立大学、駒澤大学で非常勤講師を務め、現在、岐阜女子大学南アジア研究センター特別客員准教授を務める笠井亮平さんです。
『実利論』は、あのマックス・ウェーバーが<カウティリヤの『実利論』に比べればマキャヴェリの『君主論』などたわいのないものである>と述べたほどの権謀術数の書。
『君主論』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4003400313
名立たるインドのリーダーたちが学んだという戦略書で、「不気味な大国」インドの戦略思想の根本がわかる、重要な書物です。
本書では、『実利論』が生まれた歴史的背景と、現地にいた著者ならではの視点を織り交ぜながら、この古典を解説。
現在のインドのリーダーがどの程度この『実利論』に基づいて政治を行っているのかも考察しており、今後の世界情勢を捉える上で、重要なヒントを得ることができます。
読めば、インドがアメリカや中国との関係をどう考えているのか、なぜインドが歴史的にロシアの友好国なのか、その理由も理解できると思います。
世界一の人口を持つ、多極化時代のメインプレイヤーが今後どう振る舞うのかは、国際情勢にも経済にも大きな影響を与えるものと見られます。
少なくともインド人の「マンダラ的世界観」、「外交六計」については、教養として知っておいた方がいいでしょう。
外交六計
(1)和平
(2)戦争
(3)静止
(4)進軍
(5)依投
(6)二重政策
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
インド側の大学やシンクタンクの研究者、政府関係者とインド外交や国際情勢をめぐり意見交換をしたり議論を交わしたりしていると、カウティリヤの名前や『実利論』の内容に言及されることが時々あった。とりわけ、自国を中心に置き、その周辺に円環が幾重にも広がる「マンダラ的世界観」が話題に上ることが多かった
王の幸福は臣民の幸福にあり、王の利益は臣民の利益にある。王にとって、自分自身に好ましいことが利益ではなく、臣民に好ましいことが利益である。(1-19-34)
側近の人々、敵たち、そして[何よりも]まず妻妾や息子たち[の危険]から身を守った時に、王は王国を守護することができる。[1-17-1]
[王子が王に]逆心を抱く時は[彼等は王に]報告すべきである。それが愛しい一人息子の場合は、王は彼を投獄すべきである。王が多くの息子を持つ時は、[逆心を抱く王子を]、彼が胎児や商品や騒乱[の種]にならぬような、辺境や異境に送るべきである。[王子が]人格的な要件をそなえている時は、彼を将軍や皇太子の位につけるべきである。(1-17-40~43)
ここで終わらないのが『実利論』の面白いところで、次の第一八章は、不遇の立場に置かれた王子がどう振る舞うべきかについても解説している。……父が満足せず、他の息子や妻たちに愛着する時には、森へ行くことを父に願い出るべきである。また、投獄や死の恐れがある場合には、(中略)隣国の王のもとに、庇護を求めるべきである。そこに滞在して、経済力と軍事力とを獲得し、勇猛な人物の娘を娶り、林住族長と結びつき、[父の王国の]誘惑可能分子を味方に引き入れるべきである。(1-18-5~7)
外交六計
(1)和平
和平とは「条約を結ぶこと」だとした上で、自国が「敵よりも劣勢の場合は、和平を結ぶべき」であるとしている
(2)戦争
自国が敵に対して「優勢の場合は、戦争すべきである」としている
(3)静止
「[動かずに]静観すること」を意味し、「『敵は我を、我は敵を破ることはできない』と判断した場合」の対応
(4)進軍
「拡大すること」であり、自国が「卓越した長所をそなえている場合」にとるべき方針
(5)依投
「他に寄る辺を求めること」であり、自国の「能力が欠ける場合」にとるべき方針
(6)二重政策
「和平と戦争とを[臨機応変に]採用すること」
憎悪されることは屈辱よりも悪い。軽蔑された者は自他の国民により圧迫されるが、憎悪された者は殲滅させられるからである。敵を作ることは財産を失うことよりも悪い。(8-3-14~22)
—————————-
国際政治を見ても、海外でやり取りした経験からしても、インドは理解が難しい隣人ですが、この大国の行動を理解できないと、今後は世界情勢を見誤る恐れがあります。
ビジネスパーソンの教養として、ぜひ、読んでおいてください。
———————————————–
『『実利論』 古代インド「最強の戦略書」』笠井亮平・著 文藝春秋
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4166614851
<Kindleで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0DX6LXBRC
———————————————–
◆目次◆
序 章 マックス・ウェーバーとキッシンジャーを唸らせた『実利論』
第1章 古代インドと『実利論』の誕生
第2章 国家統治で追求すべきは「実利」
第3章 マンダラ外交の真髄
第4章 インテリジェンス・ウォーを勝ち抜くために
第5章 カウティリヤの兵法--『孫子』との比較から
第6章 『実利論』から見る近現代インドの外交と政治
終 章 『実利論』から日本は何を学べるか
あとがきと謝
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
同じカテゴリーで売れている書籍(Amazon.co.jp)
お知らせはまだありません。