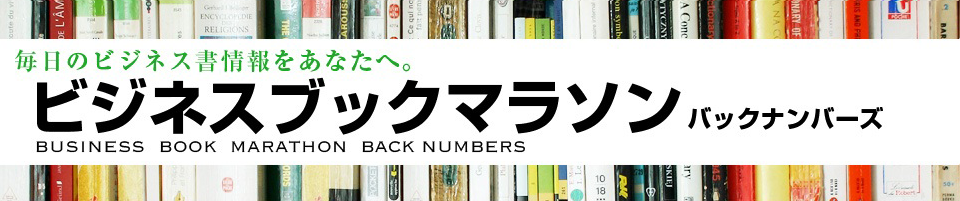【ワンランク上の英語力へ。】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534061617
土井は高校生時代、英語の偏差値が75以上ありましたが、実際の外国人との会話は、まったく歯が立ちませんでした。
「普通に会話に入っていける!」と感じたのは、ニューヨークに住んでから。
たった1年、それもニューヨークと東京の行ったり来たりでしたが、それでも飛躍的にリスニング力が高まりました。
そこで感じたことは、「やっぱり日本の英語教育は間違っている」ということ。
実際に英語で自然な会話をするためには、日本の英語教育では足りない。
では一体何をすればいいのか。
それに明快な答えをくれたのが、本日ご紹介する一冊、『英語が日本語みたいに出てくる頭のつくり方』です。
著者の川崎あゆみさんは、「第二言語習得論」をベースにした独自メソッドで、のべ5000人以上に英語を指導してきた、英語指導の専門家です。
本書では、「第二言語習得論」が教える科学的言語習得のメソッドを、わかりやすく解説。
タイトル通り、「英語が日本語みたいに出てくる」にはどうすればいいのか、実際のところを解説しています。
第1章、第2章でひと通り理論を学んだ後、第3章、第4章では、インプットとアウトプットのハウツーを解説。
第3章で述べられている、<暗記するよりも「文脈の中で7回出会う」ほうが記憶に定着する」は、とても重要なポイントだと思います。
第4章で紹介されている<アウトプット学習の正しい学び方7ステップ>もよくまとめられていて、勉強になりました。
紹介されている英語学習教材も知らないものが多く、オーストラリア帰りの土井には、アメリカ、イギリス、オーストラリアの発音が聞き分けられる、「YouGlish」が刺さりました。
これは画期的な英語学習書ですね。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
発音力と聞き取り能力は異なる能力
英語習得は、多読や会話などで「無意識的に習得される」ことがメイン
暗示的な学習を通して、読解や会話の中で何度も自然な英語のパターンに触れることで、”It’s dangerous.”や”It’s safe.” そして”How should I say it?”や”How can I express this?”といった正しい表現を、文法に意識を向けずに、使いこなせるようになっていきます。この繰り返しが、「英語が日本語みたいに出てくる」カギです
教材が難しいと、日本語の解説を読んだり、辞書を何度も引いたりして、明示的な学習がメインになりがちです。そうなると、言語習得の基盤となる暗
示的な学習をする機会が失われ、脳が自然な言語パターンを蓄積する機会を失ってしまいます
英語力をアップするには、ただ知識を詰め込むのではなく、自分が理解できるレベルの大量の英語に触れて、無意識的に脳にパターンが蓄積されることが大切
英語を使いこなす=新しい「回路」をつくること
「知る(Declarative Knowledge)」
「できる(Procedural Knowledge)」
「自動化する(Automatization)」
という3段階を経てはじめて知識をスキルとして習得したことになる
英語学習では、4つのバランスが大切
・インプット(読む・聞く)25%
・知識の勉強(暗記など)25%
・アウトプット(書く・話す)25%
・スラスラトレーニング(読む・聞く・書く・話す)25%
あなたは英語を聞き取れなかったとき、その理由を深掘りせずに「聞き取れた」「聞き取れなかった」の2択で片づけていませんか?
暗記するよりも「文脈の中で7回出会う」ほうが記憶に定着する
アウトプットのメカニズム
1.何を言うか
2.どう言うか
3.言ってみる
メタ認知
「正しい文章だったはずなのに英語が通じなかった」場合、単語や文法など構造の問題ではなく「音声として伝わりづらかった」可能性があります
—————————-
「自然に英語が聞ける、話せる」
そんな状態を目指す方に、おすすめの一冊です。
ぜひ、読んでみてください。
———————————————–
『英語が日本語みたいに出てくる頭のつくり方』川崎あゆみ・著 日本実業出版社
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4534061617
———————————————–
◆目次◆
第1章 理論編 勉強しても、英語ができないのはどうして?
第2章 理論編 「英語の正しい学び方」ってどんなもの?
第3章 How to編 インプットの「正しい学び方」(読む・聞く)
第4章 How to編 アウトプットの「正しい学び方」(書く・話す)
第5章 実践編 「じぶん英語」を育てる 「英語の正しい学び方」を実践しよう
おわりに
巻末付録
SLA/TESOL用語リスト
参考文献
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
お知らせはまだありません。