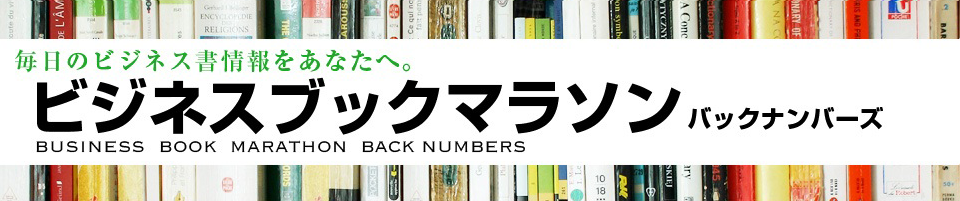【多文化時代に混乱しないために】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/400432078X
最近、外国人移住者やインバウンドの影響で、文化の衝突が度々話題になっています。
アフリカとの交流推進を目的とした国際協力機構(JICA)の「ホームタウン」構想の撤回も、記憶に新しいところです。
しかし、望むと望まざるとに関わらず、われわれはこれからインドやアフリカと付き合っていかなければならない。
「やっとアメリカや中国のことがわかってきたのに、今度はインド、アフリカかよ」という声が聞こえてきそうですが、これも時代の必然でしょう。
本日ご紹介する一冊は、文化心理学を専門とし、ミシガン大学心理学部で教授を務める著者が、多様性の謎に迫った、アカデミックな一冊。
特に、日本人には難解なアフリカ諸国の考え方について書かれており、勉強になります。
本書によると、サハラ砂漠より南の全域、「サブサハラ・アフリカ」には、「仲間だから競争をする」という、一見日本人には理解しがたい考え方がある。
いわく、「アフリカの露天商やウーバーの運転手は、たとえ同僚の利得を犠牲にしてでも、少しでも自分の利得を上げることに多大な熱意を注ぐ」。
「もし誰かに『出し抜かれ』たり、あるいは、『妨害』された場合、それは「出し抜かれ」たり「妨害」されたりしたほうの考えが甘かったということになる」のだそうです。
これが日本人とアフリカ人が揉める理由になるのですが、じつはここからが難しい。
じつはこうして成功した彼らは、決して個人主義ではなく、協調的であり、その成功を用いて親族・部族集団に貢献するのです。
「まずは個々人が成功し、そしてそれを元に集団の生存を図る」。これがわれわれが理解できないアフリカの原則なのです。
本書には他にも、われわれがよく知っていると思い込んでいるアメリカの考え方の微妙なニュアンスの違いが書かれており、彼の国と日本の自己啓発書の違いがよくわかります。
また、「関係流動性」という言葉で文化の違いを論じており、これは異文化の人と関係性を築く上で、重要な手掛かりとなると思いました。
アカデミックで難解な本ですが、書かれていることは、極めて重要。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
自分の成功は自分だけでなく、集団全体の利益にもつながるため、他のメンバーも自分の成功を誇りに感じる。このような状況では、成功した個人も「誇り」に加えて他者とのつながりを表出するのだろう
稲作や、あるいは、同じ狩りでも対象がウサギやキツネといった小動物の場合、「スター・ファーマー」や「スター・ハンター」はおそらく必要ない。このような状況では、集団の生存は多くの個人の勤勉さにかかってくるだろう
「人からも親切にしてもらえますように」と訳した部分は、ディランの詩では「レット・アザーズ・ドゥー・フォー・ユー」となっている。なんと、「レット」という使役動詞が使われているのである。つまり、「人からも親切にしてもらえますように」とは、すでに日本語の概念であり、ディランは実際には、「他の人をして自分に対して親切にふるまわせることができますように」と歌っているのだ。「人から親切にしてもらう」という受け身の社会性ではなく、「人から親切な行動を引き出し、それを自分に向けさせる」という、非常に能動的な社会性がそこにはある
個人主義者がなぜ人に対して親切なのか、その理由の一端が見えてきただろうか。人に対して親切にするのは、人から親切な行動を引きだす確率を増すための一種の方略なのだ
アメリカでは、他者に助けを求めるとは、すなわち、他者からなんらかの資源を引き出すことによって、自分の効能感を確認する作業になるのである
アメリカ人は、「私は、フレンドリーだ」とか「私は、機転が効く」というふうに抽象的な形容詞で自己を表現するという。それに対してインド人は、より具体的、状況依存的な振る舞いかたを述べる傾向がある
語調の不一致による反応時間の遅延は、日本人参加者の間で特に顕著であった。この結果は、文脈を無視すべき場合にも日本人はそれを無視できないという、文化のバイアスを示している
スタンフォード大学の文化心理学者、ジーニー・ツアイらのグループは、アジア系と比べてヨーロッパ系アメリカ人は、喜び・興奮といった覚醒度の高い肯定感情に高い価値を置いていることを示している
おそらく、それぞれの社会では、さまざまな感情に対して、その感情をどの程度感じるのが適切かという基準(つまり、規範)が存在している。そして、その基準に合った感情経験を示す人々は、周囲から肯定的なフィードバックを繰り返し受け取る可能性が高い
関係流動性が高い社会の人々は、より功利的で実利を重視し、独立した第三者の視点からコストと便益のバランスを取ることを厭わないと考えられる
—————————-
アカデミック特有の言い回しや用語、抽象度の高い表現が若干読みにくいですが、書かれている内容は、示唆に富むものばかりです。
われわれが異文化をどう理解したらいいか、これからどう共生していけばいいか、ヒントが書かれた一冊です。
ぜひ、読んでみてください。
———————————————–
『文化が違えば、心も違う?』
北山忍・著 岩波書店
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/400432078X
<Kindleで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0FN1QQR1J
———————————————–
◆目次◆
はじめに
第1章 サブサハラ・アフリカに「文化の違い」を追い求めて
第2章 日米の常識を疑う
第3章 文化と心のダイナミズム
第4章 人類史から見る文化の起源
第5章 多様性と普遍性を探る旅
終 章 文化心理学という知の冒険
あとがき
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
お知らせはまだありません。