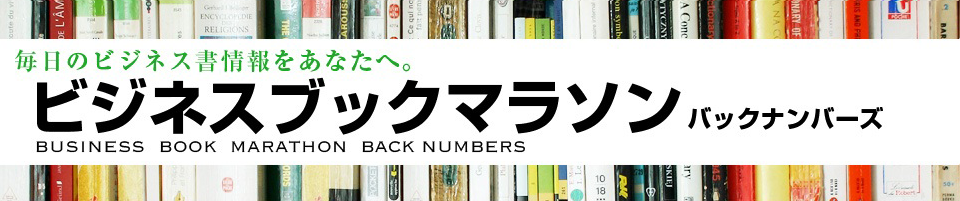【お前もファンダムにならないか?】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4297150549
本日ご紹介する一冊は、マーケティング会社トライバルメディアハウスにて、企業やブランドのマーケティング戦略、プロモーション、クリエイティブに従事してきた著者が、ファンダムを活用したタイアップ戦略を論じた一冊。
K-POPやバンド、フェス、スポーツチーム、2.5次元俳優、VTuber、声優、YouTuber、アニメ、お笑い芸人などとのタイアップ戦略について、事例も含め、細かく論じています。
ここまで読んでおわかりのように、ファンダムマーケティングは、決して簡単ではありません。
ファンダムを単に商業利用しようとすれば、その意図を悟られ、スポンサー企業もIPも脅威にさらされる。
だからこそ、IPとの相性や文脈、ファンダムの理解が重要になるのです。
本書では、特に上手く行った事例として、オーディオテクニカと声優姉妹である内田真礼さん、内田雄馬さんのタイアップを挙げていますが、この企画では、
「最高!」
「こんなの聴けちゃっていいんですか!」
「オーディオテクニカさん、内田姉弟を選んでくれてありがとう!」
と感謝のコメントが多く寄せられたようです。
もちろん、失敗すれば炎上リスクもあるわけですが、本書を読む限り、ファンダムと一緒に創るマーケティングは、想像以上にクリエイティブで面白そう。
ビジネスの基本である「喜んでもらう」が根底にあるマーケティング手法なので、きっと前向きに取り組めると思います。
本書では、このファンダムマーケティングを成功させるためのノウハウや注意点が書かれていますが、なかでも、「IPと自社をつなげる8ヶ条」、低予算でインパクトが見込める「セグメントマス」を見つける5つの方法、「ありがとう」と言われるコンテンツを生み出す2つの視点、ファンダム内での情報伝搬の設計の仕方は勉強になりました。
オーディオテクニカ以外にも、エスエス製薬とVTuberグループ「ホロライブ」とのキャンペーン、リクルートと総勢19名のアーティストとのタイアップ、志摩スペイン村と国内最大のVTuberプロジェクト「にじさんじ」所属の周央サンゴさんとのタイアップなど、興味深い事例が掲載されており、マーケティングの参考になると思います。
また、ターゲットをサウナトライブに絞ったヘアケア製品の「UNSAA-アンサー」、強力なスニーカートライブであるストリートアパレルブランドの「SAPEur(サプール)」など、中小企業でも真似られるファンダムマーケティングの事例が紹介されています。
規模の大小を問わず、マーケター、経営者、商品開発者にとって勉強になる本だと言えるでしょう。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
真の意味で有効なタイアップとは、プロモーション領域のみならず、ブランディング領域にも強い効果を与えることができるもの
どんな宗教であれ、そこに共通している1つの感情。それは「救い」です。(中略)推しに対してファンダムが求めるものも、まさに救いです。推しがいることで、辛い現実から逃避できる、頑張ろうと活力をもらえる。推しがいることで、世界の景色が変わる。推しがいることで、私は私でいられる、私は救われる
推しの中で言われる用語に不思議と宗教や信仰に関わる言葉が多いのも興味深いです。たとえば、「尊い」「召される」「神」「お布施」「布教」「聖
地巡礼」といった具合に
価値観は、昔に比べて物質的主義から精神的充足主義に変化しています
ファンダムが消費者じゃないとしたら、いったい何なのでしょうか。答えは、「同志」です
企業やタレントからの一方通行なコミュニケーションや企画ではファンダムは動きません。そこに必ず「意味」を見出します。
それは推しの価値になるのか?
推しの魅力が際立つものなのか?
自分がそこに介在する意義はあるのか?
■エスエス製薬とVTuberグループ
「ホロライブ」とのキャンペーン生配信では、ファンダムに人気の「くしゃみ」の要素が巧みに取り入れられました。たとえば、花粉症にまつわる体験談クイズや、指定されたシチュエーションでの「くしゃみゲーム」が実施され、「くしゃみがかわいい」とファンダムから好評を博しました。VTuber
の文化において「くしゃみ」は人気の要素であり、関連するまとめ動画が制作されるほどで、この「くしゃみ」文脈を企画に落とし込むことでファンダムとの共感、アレジオンとの接続性、意味性を強化したのです
ニッチだけど可処分精神が高いゾーン(=セグメントマス)を見つける5つの方法
(1)専門メディアで見つける
(2)キュレーターから見つける
(3)専門のファンダムに尋ねる
(4)ライブ会場の規模で見つける
(5)3-4番手を見つける
■「ありがとう」と言われるコンテンツを生み出す2つの視点
・「わかってるね感」
・「そうきたか感」
■企業名もしくは商品名とIPがセットで語られる秘訣
(1)コンテンツの一次発信を必ず企業から始める
(2)企業とIPの結びつきをIP側の発信に必ず入れ込む
—————————-
ファンダムが単なるファンとどう違うのか、その精神構造がよくわかり、企業がどうタイアップすればいいか、かなり具体的なところが見えてくる好著です。
これは、ひさびさに面白いマーケティング書に出合いましたね。
ぜひ、読んでみてください。
———————————————–
『ファンダムマーケティング』
高野修平・著 技術評論社
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4297150549
<Kindleで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0FM741BKG
———————————————–
◆目次◆
はじめに
第1章 ファンダムとファンダムマーケティングを理解する
第2章 ファンダムマーケティングの目的を決める
第3章 IPのジャンルごとの特性を把握する
第4章 ファンダムを自社に接続する
第5章 ファンダムマーケティングに「ありがとう」と言ってもらえるコンテンツと情報伝搬を設計する
第6章 ファンダム以外に広げる
第7章 ファンダムマーケティングの効果測定をする
第8章 ファンダムマーケティングの真髄
第9章 ファンダムマーケティングの疑問あれこれ
おわりに
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
同じカテゴリーで売れている書籍(Amazon.co.jp)
お知らせはまだありません。