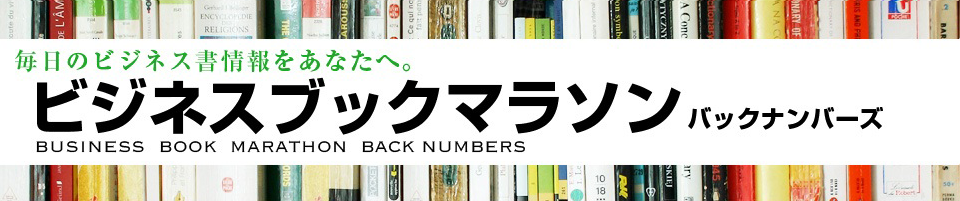【売れてます。】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4106111012
本日ご紹介する一冊は、今、最も注目されている文芸評論家、三宅香帆さんによる、話題の新書。
ベストセラーとなった『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』も、上手いタイトルでしたが、今回も上手い。
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4087213129
予想通り、よく売れているようです。
人間誰しも、「話が面白い人」と思われたいでしょうが、そうなるためにはインプットが重要。
本書では、そのインプットに関して、第一部で5つの視点を提示しています。
5つの視点とは、以下の通りです。
(1)<比較>ほかの作品と比べる
(2)<抽象>テーマを言葉にする
(3)<発見>書かれていないものを見つける
(4)<流行>時代の共通点として語る
(5)<不易>普遍的なテーマとして語る
小説であれ映画であれ、作品に触れた時、この5つの視点を意識して観る。
そうすることによって、アウトプットが驚くほど変わってくるのです。
第二部は、この五つの視点を使って書かれた、三宅香帆さんの過去の評論。
小説に限らず、漫画、映画、ビジネス書なども登場するので、ビジネスパーソンにとってはとっつきやすいと思います。
なかでも面白かったのは、<あってもいいはずなのに、なぜか、ないもの。それを見つけるだけで、鑑賞体験はぐっと深くな>る、という部分です。
『となりのトトロ』に、なぜ電化製品が登場しないのか、映画『国宝』は、歌舞伎の話なのに、なぜファンの姿が描かれていないのか、著者の解説を併せて読むと、これまでに見えなかった、作り手の思想が見えてきます。
他にも、「成瀬」シリーズが従来の「青春」物語を更新したという話、フィギュアスケート漫画『メダリスト』が「コーチ側の熱狂」を描いているという話など、大変興味深く読みました。
著者と同じだけのインプットをするのは難しいと思いますが、この視点を学ぶだけでも、価値があると思います。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
教養があるとは、社会や人生の「ネタバレ」をたくさん知っているということ。だから教養のある人は話が面白いのだと思います
(1)話を仕込む
(2)話を解釈する
(3)話すときに(2)を使う
なにかを読んだとき、それを「ネタ」にするための物語鑑賞「五つの技術」
(1)<比較>ほかの作品と比べる
(2)<抽象>テーマを言葉にする
(3)<発見>書かれていないものを見つける
(4)<流行>時代の共通点として語る
(5)<不易>普遍的なテーマとして語る
ポイントは「変化」や「結末」に注目することです。
・この作品は主人公がどんな変化を遂げているか?
・とくに力を込めて描かれているのはどんな場面か?
・最終シーンはどんな結末で終わっているか?
あってもいいはずなのに、なぜか、ないもの。それを見つけるだけで、鑑賞体験はぐっと深くなります。そして話のネタに、変わるのです。
例):『となりのトトロ』には、電化製品がほぼ登場しない
著者が書いた映画『国宝』のメモ
発見:歌舞伎の話なのに、ファンが描かれていない!
大好きな「成瀬」シリーズの魅力を解説したい。このシリーズの面白さ。それは従来の「青春」物語を更新したところにある、と私は思っている
90年代:教室の外にある死
00年代:教室の閉塞感
10年代:教室からの解放
「成瀬」シリーズは、『あまちゃん』のテーマを更新し、2020年代のモードを見せている。–もはや地元を出る必要はないのだ。成瀬あかりは、地元を出ず、地元で友人と生きることを肯定する
フィギュアスケート漫画『メダリスト』の魅力について書くと、この漫画の面白さとは「コーチ側の熱狂」が描かれているところにある
「実力も運のうち」なんて言葉が出てきてしまうと、少年漫画というジャンルを支えている人々の思想–もっと強くなりたい!–を根底から揺らがせるようにも思う。しかしそんな時代にあっても、人々の「強くなりたい」「強くありたい」という欲望には変わりがないのだ。変わったのは、強くあるために何が必要なのか? という部分だけなのだ
しかしコントロールできないものに立ち向かうのは、怖い。こんなに貯金して努力して人生設計して明日をコントロールしようと生きているのに、世界はどうやらアンコントローラブルである。–その恐怖が、直木賞候補作たちに「制御不能な存在」を描かせている
—————————-
注目の文芸評論家が、どんな視点で作品を観ているのかがわかり、大変勉強になりました。
元々連載していたものを使い回している関係上、文体やテーマずれなど、若干不自然な部分が目立ちますが、それをマイナスしてもなお、面白い本です。
これぐらい鋭い視点が持てれば、話は間違いなく面白くなると思います。
ぜひ、読んでみてください。
———————————————–
『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』
三宅香帆・著 新潮社
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4106111012
<Kindleで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0FMDBV369
———————————————–
◆目次◆
まえがき
第一部 技術解説編
1 話が面白いという最強のスキルについて
2 味わった作品を上手く「料理」してネタにする
3 具体例でわかる! 物語鑑賞「五つの技術」
4 「鑑賞ノート」をつけてみよう
5 読解力があればコミュニケーション上手になれる
第二部 応用実践編
1 <比較>ほかの作品と比べる
2 <抽象>テーマを言葉にする
3 <発見>書かれていないものを見つける
4 <流行>時代の共通点として語る
5 <不易>普遍的なテーマとして語る
あとがき
付録 話が面白くなるブックリスト
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
同じカテゴリーで売れている書籍(Amazon.co.jp)
お知らせはまだありません。