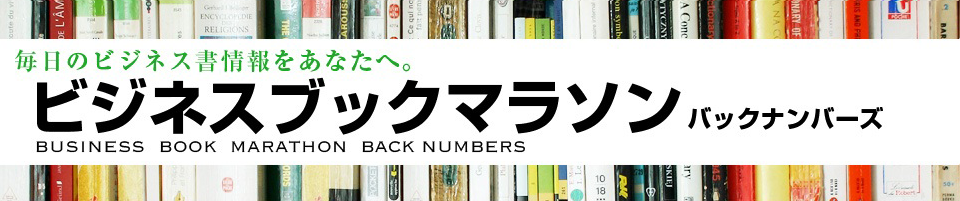【必読。壮大な土と生命の物語】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4065378389
これまでBBMでは、『土の文明史』や『ミミズの話』など、いくつか土に関する本を紹介してきました。
『土の文明史』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4806713996
『ミミズの話』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4864100306
なぜかというと、われわれの文明を支えているのは土であり、国家衰退の原因となるのもまた土だからです。
土がなければ作物はできず、人間は飢えて死んでしまう。
しかもその土は、生命と並び、人間には作り出すことができないのです。
本日ご紹介する一冊は、この土と生命の46億年史を、河合隼雄学芸賞受賞の土の研究者がつづった一冊。
正直、これまでに読んだどんな土の本よりも面白かったです。
土とは何か、どこから来たのか、なぜ土から生命が生まれるのかといった謎が、納得いくまで丁寧に書かれており、いかに土が希少で尊い存在なのか、実感できる内容です。
かなり高度な内容が書かれていますが、著者のユーモアあふれる文章のおかげで、これまで知らなかった土と生命の秘密が、根本から理解できると思います。
なぜマツタケ1本が数千円するのに、エリンギや舞茸は100円で買えるのか、なぜ、本来毎日170リットルの水を必要とする人間が、1日2リットルの水分摂取で済んでいるのか、下痢止め薬や珪藻土マットなどの便利なアイテムはどんな原理で成り立っているのか、なぜ粘土はネバネバするのか、われわれの生活の身近な疑問も解消でき、強烈な「アハ体験」が続くこと、間違いなしです。
サイエンスの本で、読み終わるのがこんなに辛い本は、初めてでした。
読者が『サピエンス全史』が好きな人なら、間違いなく気に入る本だと思います(個人的には、『サピエンス全史』よりも本書の方が感動しました)。
『サピエンス全史』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4309862934
ぜひ、読んでみてください。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
生と死は、生物と無生物は、土でつながる。多くの陸上生物は土から命の糧を得て、やがて遺体は土の一部になる
生物の誕生の前に地球上には粘土が登場し、生命と土が生まれる下ごしらえをしてきた。なお、粘土とは2マイクロメートル(2ミリメートルの1000分の1)以下の粒子と定義される。粘土より大きい粒子は、サイズ(粒径)に基づいて分類され、小さいものから順にシルト、砂、石レキ(礫)に分類される
半導体に使うケイ素はイレブンナイン、つまり99.999999999パーセントの純度を満たす必要がある。主たる原材料は中国産の石英砂だが、あらゆる地下資源は有限だ。ケイ素頼みの現代文明は、砂に依存した「砂上の楼閣」でもある
鬼界カルデラの噴火後7300年のあいだに30センチメートルの土ができたとすると、100年で4ミリメートルの土ができる計算になる
ダイヤモンドと黒鉛、活性炭のように、粘土も結晶構造と純度が違えば、異なる性質を備えた粘土鉱物になる。第1列のケイ素と第2列のアルミニウムだけの二層構造ならカオリナイトという粘土鉱物になり、ファンデーション(白粉)や陶磁器の原材料として使われる。第3列のケイ素も加わった三層
構造ならスメクタイト、バーミキュライト、雲母(マイカ)といった粘土鉱物になる。スメクタイトは水やイオンをよく吸収するため、猫砂、下痢止め薬の主成分となる
粘土のマイナス電気はプラスの電気を帯びた陽イオン(例えば、カルシウムイオン)を引き付ける。これを吸着という。陽イオンは単独ではなく、取り巻きの水分子も同伴してくる(水和)。この結果、粘土表面を薄い水膜が覆うことになる。そこに加えて、細かな粒子間には毛管張力によって水が入り込み、粘土粒子どうしをくっつけようとする力(分子間力と水素結合)が働く。これが、造岩鉱物とは違って粘土に水を加えるとネバネバする理由である
粘土は生命誕生の場としてだけでなく、かつて「生命の一部だった」
自らを再生し情報を伝達できる物質は、自然界では粘土と遺伝子しか見つかっていない
キノコは酸性に強い。樹木が登場してからリグニンが分解できずにカビや細菌が困っていた石炭紀(3億年前)、白色腐朽菌と呼ばれるキノコが全く新しい酵素を生産できるように進化した。マツタケ、エリンギ、シイタケのご先祖様だ
—————————-
近年、サステナビリティという言葉が流行っていますが、土の知識なくして、サステナビリティの議論もないと思います。
願わくば、この本を読み切れるだけの知性と、この知識を踏まえた議論ができる政治家が今後、選ばれんことを。
本書を読めば、土に限らず、われわれが自然から受けている恩恵が何なのか、人類がそれとどう付き合ってきたのか、深いところまでよくわかると思います。
土を知らずして、教養人は語れない。
ぜひ、読んでみてください。
———————————————–
『土と生命の46億年史』
藤井一至・著 講談社
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4065378389
<Kindleで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0DR2HM7ZX
———————————————–
◆目次◆
はじめに
第1章 すべては粘土から始まる
第2章 生命誕生と粘土
第3章 土を耕した植物の進化
第4章 土の進化と動物たちの上陸
第5章 土が人類を進化させた
第6章 文明の栄枯盛衰を決める土
第7章 土を作ることはできるのか
おわりに
巻末付録
参考資料
さくいん
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
お知らせはまだありません。