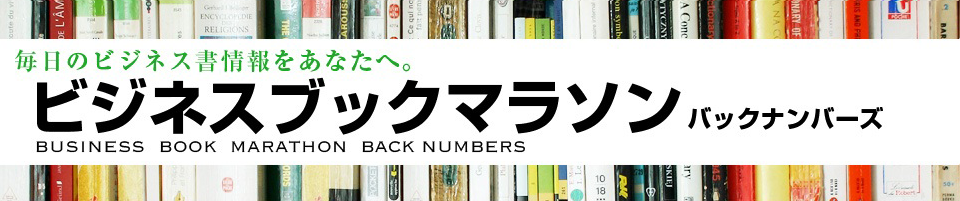【天才作詞家のヒット法則】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4396618409
どんな世界にも、何かを始めて10年くらいで大成功してしまう人というのがいるものですが、そういう人は決まって、成功を因数分解できています。
何が変数かを見極め、その道のベテランにはない感性や視点で、変数にまったく新しいアプローチで迫っていく。
そんな人の思考は、たとえそれがビジネスの世界ではなくても、勉強になる要素があるものです。
本日ご紹介する一冊は、東大で数学、哲学を学び、その後、作詞作曲家、音楽プロデューサーとして大成功した、ヤマモトショウさんによる言葉とアイデアの作り方。
SNSで30億回再生されたというFRUITS ZIPPERの『わたしの一番かわいいところ』の作詞作曲編曲を担当した人物といえば、ピンと来る人は多いのではないでしょうか。
本書が面白いのは、著者が作詞に対して、論理的かつ再現性の高いやり方でアプローチしているところ。
音楽を構成する要素は何か、良い歌詞の「良い」とは一体何かといった基本的なところからヒット曲の条件を丁寧に紐解き、自身のアプローチを紹介しています。
音楽を構成する3大要素
・メロディ
・コード
・リズム
良い歌詞 の「良い」とは
(1)歌い手にとって良い
(2)ファンにとって良い
(3)文・詩として良い
(4)耳に良い
このような、思考の歩幅が狭い、丁寧なロジックを読んでいけば、何の分野でも、成功の糸口がつかめるもの。
加えて、作詞ならではの要素、音楽だからこそ考慮しなければならない点も述べられており、こちらも勉強になります。
作詞に興味のある方はもちろん、クリエイティブのヒントを探している方、ヒット商品を手掛けたいと考える方にとって、有用な視点が見つかると思います。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
詞は「歌詞」であり、必ず音楽と一緒に存在しています。歌詞のない音楽はもちろん存在しますが、音楽のない歌詞というのは存在しないわけです
詞先で歌詞を書く場合に最も自然な方法は結局、自分でもメロディをイメージしてみること、つまりは作曲をしてみることでしょう
「歌詞らしさ」というのは、やはり作曲的行為、音楽的創作と不可分です
「メロディに合ってない」という観点にはいくつかのレイヤーが存在します。まず、明らかにメロディの音数に対して語数が合っていないものです
二つ目は、「メロディと歌詞が字数ではない理由で合っていない」と思われるパターン
音楽というのは基本的にはあるパターンの繰り返しです。(中略)そのため、歌詞はその繰り返されるパターンを意識したものである必要があります
あなたが作詞家になりたいのであれば、「好きな○○は何ですか?」という質問に100個くらい、すぐにエピソードをそえて答えられるか確認してみてください
私はむしろ好きではなくて「嫌い」のほうから創作をスタートすることを薦めています
「好き」よりも「嫌い」のほうがより個人的でありながらも、共有される可能性を持っているもののように思われます
「何を計算しないといけないのか」を考える
太田裕美『木綿のハンカチーフ』(作詞:松本隆)
この楽曲が、歌詞として最も優れている点の一つは「上京する側」「残される側」どちらにも共感されるポイントを残しているところ
松田聖子『赤いスイートピー』
「○色(○に入るのは具体的な色の名前ではない)」という形のリリックは松本氏の歌詞に最も特徴的なものの一つ
日本では「–のサンバ」というタイトルの曲がこれまでに何回もヒットしているのですが、そのほとんどがサンバではないのです
小林明子『恋に落ちて-Fall in Love-』(作詞:湯川れい子)
「ダイヤルを回す」という言葉に「ダイヤルを回す」という意味しかなかったとしたら、この歌詞には何の奥行きもないでしょう
—————————-
昔、ある有名作曲家に「土井さん、歌詞やってみない?」と言われて怖気づいた経験があり、気になって手に取った本でしたが(笑)、思いがけず仕事のヒントが見つかりました。
これは、おすすめの一冊です。
ぜひ、読んでみてください。
———————————————–
『歌う言葉 考える音』ヤマモトショウ・著 祥伝社
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4396618409
———————————————–
◆目次◆
はじめに
01 作詞家という仕事
02 歌詞の書き方
03 良い歌詞とは何か
04 「歌詞の意味がわからない」の意味がわからない
05 個性について
06 歌詞と哲学
07 音楽と数学
08 歌詞は共感
09 アイドル
10 タイトル
11 言葉の情報収集
12 大考察時代に寄せて
13 AIと音楽
14 音楽教育について
おわりに
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
同じカテゴリーで売れている書籍(Amazon.co.jp)
お知らせはまだありません。