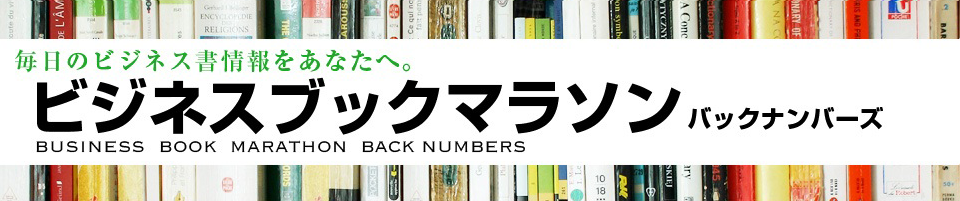【仕事の段取り】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/475692395X
本日ご紹介する一冊は、限られた時間で成果を出すための考え方と時間管理術を述べた一冊。
著者は、公的機関や民間企業でプロジェクトマネジメントやスケジュール管理研修を行う、コンサルタントの飯田剛弘(いいだ・よしひろ)氏です。
2018年に出ていた同名の書籍を改訂したもので、これからの時代により合った方法やヒントを新たに盛り込んでいます。
<「人はやることを忘れる」という前提に立ち、思い出すための仕組みを作っていく>
<仕事の効率を上げるには、切り替えコストとムダを減らすこと>
という、大前提を述べた後、打ち合わせを1時間ではなく分単位で行う、朝一番か帰り際の15分~30分を作業仕分けに充てるなど、具体的なスケジュール管理に踏み込んでいます。
<5分以内に終わる仕事なら、すぐにやる><締め切りがあり、15分以上かかる仕事やミーティングなら、通常のカレンダーに予定を入れる>というように、仕事を作業時間で分ける方法も有効だと思います。
また、仕事ができる人が必ずやっている、相手のスケジュールの把握、情報管理のコツなども紹介されています。
なかでも心したいのは、<「価値を生み出す仕事」で予定を埋める>こと。
何が価値を生むのか、どうすればムダな作業がなくなるのか、突き詰めて考えることで、著者が考えるような理想の状態が実現できると思います。
プロジェクト管理を専門とする著者が書いているだけあって、仕事を進めるための現実的な考え方が示されているのがポイント。
理想主義が行きすぎてうまく仕事が進まない、という人には特におすすめの一冊です。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
「人はやることを忘れる」という前提に立ち、思い出すための仕組みを作っていくことが重要
仕事の効率を上げるには、切り替えコストとムダを減らすことが重要
「探しもの」をする時間はムダ
「仕事の時間割」を作れば集中力も高まる
時間の単位を分や秒で捉え、1時間病を脱却する
5分以内に終わる仕事なら、すぐにやる
締め切りがあり、15分以上かかる仕事やミーティングなら、通常のカレンダーに予定を入れる
毎日、朝一番か帰り際の15分~30分を、誰にも邪魔をされない時間として確保し、作業仕分けを試してください
仕事によって、スピード重視なのか品質重視なのかは変わってきます
難しそうな問題や仕事は、小分けにしてハードルを下げる
問題解決のために、「悩む」のではなく「考える」
相談や確認をお願いしたい人のスケジュールを把握することは、自分の仕事をスムーズに進めるために重要
タスク置き場とは、やらなければいけない仕事関連の資料や情報が保管・管理されているところです。タスク置き場の数が多いと、探しものの数が増えます
メモをできるだけ一か所にまとめて管理する
ボックスやケースの中も「デッドライン」で管理する
メールは「フォルダ分け」よりも「検索」で一瞬で見つけるのが基本
得意だと感じる時間帯は、人それぞれ違います。まずは自分が最も集中でき、パフォーマンスの上がる時間帯がいつなのかを把握することが大切です。そして、その時間帯を最大限活用するために、外部から邪魔されず、集中できる環境を作っていきましょう
ゴールイメージは仕事の依頼者の頭の中にある
「価値を生み出す仕事」で予定を埋める
完璧を追わず、少しでも進んだらOKと肯定する
—————————-
ムダを省き、仕事をサクサク進めるための心構えとノウハウ、ツールが紹介されています。
仕事の進め方を見直ししたい方は、ぜひ、読んでみてください。
———————————————–
『決定版 仕事は「段取りとスケジュール」で9割決まる!』飯田剛弘・著 明日香出版社
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/475692395X
<Kindleで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0F1XHCG6J
———————————————–
◆目次◆
はじめに
第1章 なぜギリギリになってしまうのか?
第2章 アタマの切り替えを減らす
第3章 仕事のスケジュールを組むための「仕分け術」
第4章 「いつまでに」を癖にする「デッドライン」の守り方
第5章 振り回されない「コントロール術」
第6章 探す仕事を減らす「タスク置き場」の作り方
第7章 習慣とテクノロジーで進化する時間管理
第8章 仕事のやり直しを防ぐ「逆算思考術」
第9章 時間は金よりケチって使え!
第10章 よくある失敗とその対策
おわりに
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
同じカテゴリーで売れている書籍(Amazon.co.jp)
お知らせはまだありません。