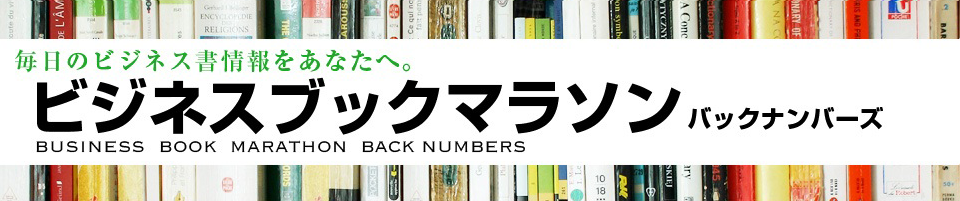【今井むつみ先生最終講義】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4296124382
本日ご紹介する一冊は、AI時代の到来を受けて話題となったベストセラー、『言語の本質』の著者であり、認知科学の専門家、今井むつみ先生による慶應大学SFC最終講義。
『言語の本質』
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4121027566
氏は2025年3月に慶應大学SFCを定年退職したそうですが、本書には、氏が28年間続けてきたという「認知心理学」講義のエッセンスが書かれています。
人間がどうやって世界を捉え、認知しているか、その仕組みを知り、より良く生きるためのヒントを与えてくれる内容で、学生たちへのアドバイスとエールが詰まっています。
前半は、人が何かを「見る」時のクセ、文脈が「見る」ことに与える影響、見落とし、記憶の書き換えなど、人間はこうも不完全なのかと驚く内容が書かれています。
中盤以降は、確証バイアスやそれを増幅させるエコーチェンバー現象、流暢性バイアス、思い込みの塊であるスキーマなど、教科書通りの認知心理学の実験・知識が紹介されています。
昨今のSNSのアルゴリズムを考えると、ここを知っておくことは、インターネット企業の搾取から身を守ることにつながると思います。
講義の中で感動的なのは、一流の人間、クリエイティブな人間がやっている「アブダクション」について書いた部分で、人間らしさ、人間の持つ可能性についてコメントされています。
<アブダクションが「知識を拡張する」>
この性質がある限り、今後も人類は知識を拡張し、それをシェアしていける。
不完全なはずの人間の認知の仕組みがもたらす恩恵に、思わず感謝したくなる瞬間です。
AIに対抗する手段として読むも良し、学習のヒントとして読むも良し、子育てのヒントとして読むも良し。
自己啓発的に読める、興味深い認知心理学の本だと思います。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
心理学に限らず、実験をすれば何かしらのデータが得られます。しかし、仮に同様の実験を行って同じデータを得られたとしても、そこから導かれる結論が人によって異なる、ということは往々にして起こります。それは、データと結論の間に「人間による解釈」の過程が存在するからです
私たちは何となく、「自分の見ている世界」と「隣の人が見ている世界」は同じだと思っています
私たちの「見る」という行為は、外界にある対象を網膜に映したイメージから始まります。しかしこのとき、網膜に映るものをカメラのようにパシャッと切り取って認識し、記憶しているのではありません。網膜に映ったものを知覚するまでには、脳内でものすごくたくさんの工程を経ていることがわかっています。まず画像はすべて、脳の最後部にある視覚野に送られ、「線」や「色」などのバラバラの要素に解体されます。これらの要素は脳の別の場所でそれぞれ処理され、再び組み立てられることになります。この解体と再構成によって、人はものを「見て、対象を認識する」ことができるわけです
私たちはものを認識するときには、無意識に「かげ」の情報を使っている
文脈によって、見える”もの”が変わる
後から聞いたことばのイメージで「見たはずのもの」が書き換わる
私たちにいくら論理的思考や確率的思考ができる能力があるとしても、ちょっとしたことでその思考を無視し、「自分のスキーマに合うか」という一点で何かを判断してしまうことが起こりうる
エコーチェンバーは、人間の「確証バイアス」を、インターネットが人為的に増幅させているもの
「自分の労力の過大評価」と「他者の労力の過小評価」
アブダクションが「知識を拡張する」
人間は、論理を突き詰めて考える、つまり熟慮するよりも、スキーマを使って省エネですばやく判断することを圧倒的に好んいる
AIは身体を持たないので、直接観察した世界を見ることができない
結局、究極の知識がどのように創られるかといえば、「知識を発見して使い、推論をして、そこでさらに新しい知識を創り、それをさまざまな場で使う練習を重ね、身体の一部にする」ことによってしかありません
—————————-
最終講義本特有の感動を味わいながら、認知心理学の基本が学べる一冊。
おそらく本書をきっかけに、著者と同じ道を目指す若者も登場するのではないでしょうか。
良い本です。ぜひ読んでみてください。
———————————————–
『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』
今井むつみ・著 日本経済新聞出版
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4296124382
<Kindleで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0F9F1JDN1
———————————————–
◆目次◆
はじめに
開講 AI時代を幸せに生きるには
そもそも私たちは、「客観的」に世界を見ることができるのか?
「記憶」はあまりにも脆弱
人は基本的に「論理的な思考」が苦手である
「確率」よりも「感情」で考えてミスをする
「思考バイアスに流されている状態」は、思考しているとはいえない
スキーマがあって初めて、高度な思考が成り立つ
情報処理能力や記憶の制約が生み出した人間独自の思考スタイルとは?
アブダクションによって人は、知識を拡張し、因果関係を解明し、新たな知識を創造している
一般人と一流の違いは、アブダクションの精度にある
AIは記号接地しない=新しい知識・生きた知識を生み出さない
AIが生み出すのは、「一般人の平均値」。唯一無二のパフォーマンスを生み出せるのは、人間である「あなた」
「得手に帆を揚げる」という生き方
おわりに
参考文献・資料
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
同じカテゴリーで売れている書籍(Amazon.co.jp)
お知らせはまだありません。