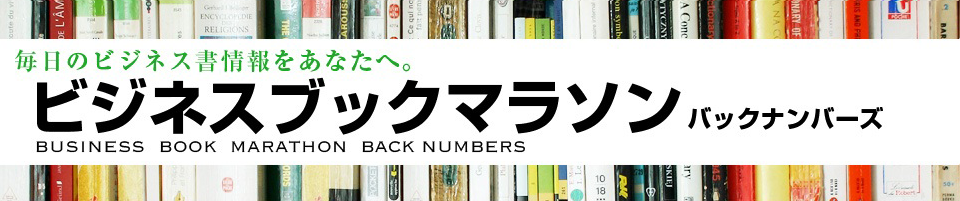【傑作です。】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4296071068
本日ご紹介する一冊は、怠け者の大学4年生がChatGPTに出会い、プログラミングに取り組んだら、教授に褒められ、海外論文が認められ、ソフトウェアエンジニアとして就職できたというお話。(ここまですべて帯の文言です・笑)
著者は、愛知県豊橋市生まれの大塚あみさん。
2024年3月に大学を卒業し、ChatGPTがきっかけでIT企業にソフトウェアエンジニアとして就職したという、面白い経歴の方です。
本書には、著者がXの投稿をきっかけに始めた、100日間、何かプログラムを作って投稿するという「#100日チャレンジ」の軌跡が書かれています。
何もないところから学習を始めても、人はこんなに偉大になれるんだという、驚きと感動にあふれた書籍です。
著者がいかにプロジェクトに取り組み、課題を解決していったか、そのプロセスを知ることで、これからの時代に活躍する人材の資質も見えてくるのではないでしょうか。
土井がこの女性を見ていて感じ取った資質は以下の通り。
・やりたいこと、試したいことがある
・抽象化思考、アナロジー思考
・人を上手に頼れる(先生、ChatGPT)
・素直さ
・人の期待に応えたい気持ち
・向上心
・モチベーション維持の技術、習慣術
・他人からの評価より課題に取り組む粘り強さ
・あるものでまかなうエフェクチュエーションの考え方
・記録するマメさ
これはそのまま、AI時代に活躍する人物の条件になりそうです。
どんなに優れたツールがあっても、それを使いこなし、何かを成し遂げるには必要な条件がある。
それがまさに上に列挙した要素なのかもしれません。
また、本書を読むことで、AIという知性と上手にコラボするためのコツも見えてきます。
理論や式を提供することで、相手の知性を高めるというのは、これまでにも会議の場などで行われてきたことですが、対AIにおいても重要なのだと認識させられました。
新しい時代の働き方、生き方、能力開発のヒントとなる一冊です。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
ChatGPTが生成した文章は、ゴミサイトの記事と比べて何が明確に違うのか? 答えはすぐに分かった。AIが生成した文章には「個人的な感想」や「経験」が全く含まれていないのだ
その光景をぼんやりと眺めていると、ふと建物の設計とソフトウェアの設計の類似点に気づいた。建物はまず建築士が詳細な設計図を描き、顧客はそれを確認して発注する。積み木で家を作るようにトライアルアンドエラーを繰り返すわけではない。一方、本や授業で紹介されているプログラミング学習は、言語の文法やコードを書くことに重きを置いている。設計や上流工程については理論で学ことはあっても、実際に開発を経験するのは会社に入ってからの人がほとんど。オセロのプログラムを作る際、私はプロンプトを考え、ChatGPTに具体的な指示を与えてプログラムを生成していた。これはまさに上流工程の設計ではないか?
初心者でも上流工程から学ぶことで、効率的にプログラミングの本質を理解できる
私は、“Fake it till you make it”という言葉が好きだ。日本語にすると「成功するまで成功者のふりを装う」という意味になる。最初から完璧でなくても、成功しているふりをすれば、やがて本物の成功にたどり着ける
勢いに乗った私は、次の日にはポーカー、その翌日には電卓、そしてDay4には将棋を投稿した。これらもすべて過去に作った作品で、多少のバグ修正を加えたりはしたものの、実質的にはストック(手持ち品)の流用だった
ChatGPTはプログラムの骨組みを作るのには非常に便利だが、デザインの微調整や人間が感じる美しさのような主観的な要素は、やはり自分で作らなければならない。数学的な美しさや対称性はChatGPTで表現できるものの、ゲームのビジュアルや操作感といった直感的な部分は人間の感覚が不可欠なのだ
■著者が考える自分の資質
(1)手を抜くことに全力を尽くす
(2)興味を追いかけるときには、頑張っているという意識がない
(3)新しいことに飛び込むのを躊躇わない
「プログラマーは、与えられたタスクに対してコードを書いて、動くものを作る。でも、エンジニアはそれだけじゃない。システム全体を見渡し、効率的なアルゴリズムを選定し、どのようにしてそのシステムを実現して拡張できるか、長期間にわたって運用できるかを考えなければならない。そのためには、数学や論理学の知識が欠かせないんだ」(先生の言葉)
「そう、再利用だ。一度作った関数やクラスなどを他のプログラムでも簡単に使えるように設計することは、開発における基本中の基本だ(以下略)」(先生の言葉)
—————————-
最後の方で先生が語った、「私がサポートできるのは、何かをやり始めた人に対してだけだ。何も考えない人には適切な手助けができない」というセリフは、おそらく主語をAIに変えても成立する話だと思います。
これからは、スキルよりも「やりたいこと」がはっきりしている人が活躍する時代になりますね。
著者が辿った軌跡を楽しく読むだけで、これからの時代に必要な考え方が身につく、素晴らしい書籍です。
傑作です。ぜひ、読んでみてください。
———————————————–
『#100日チャレンジ 毎日連続100本アプリを作ったら人生が変わった』大塚あみ・著 日経BP
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4296071068
<Kindleで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0DQ81M5TF
———————————————–
◆目次◆
ステップ0 プロローグ
ステップ1 チャレンジ開始
ステップ2 チャレンジの意義
ステップ3 作品は私次第
ステップ4 私と誰かの未来
ステップ5 理想と現実
ステップ6 最適解を求めて
ステップ7 エピローグ
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
同じカテゴリーで売れている書籍(Amazon.co.jp)
お知らせはまだありません。