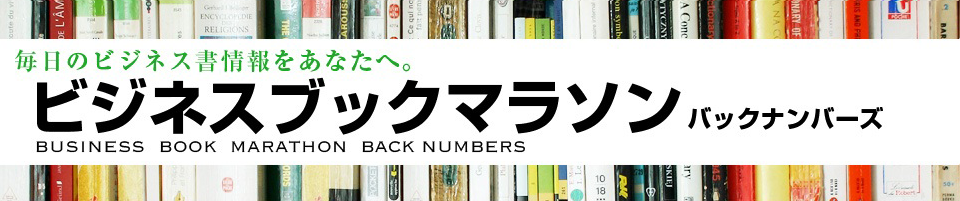【これは必読。】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4087213501
本日ご紹介する一冊は、今どきバズる書き方をマスターできる本。
著者は、「47NEWS」で300万超のPVを連発する、共同通信社デジタル事業部担当部長の斉藤友彦氏です。
著者がデジタル向けの記事に取り組んだのは、2021年。共同通信社に「デジタルコンテンツ部」が新設されたのがきっかけだそうですが、そこで著者は、衝撃的な事実に気づきます。
それは、新聞記者が少ないスペースに情報を詰め込むためにやっている伝統的な「逆三角形スタイル」が、若者に忌避されているという事実です。
著者は、第1章でこの「逆三角形スタイル」がどんなものかを解説し、そのどこが若者に嫌われる原因なのか、若者たちの言葉を引用しながら紹介。
具体的にどう変えればネットでバズる書き方に変わるのか、新聞スタイルと比較しながら述べています。
その要点をまとめたのが、135ページに書かれた「デジタル記事の書き方のおさらい」ですが、本当に書けるようになるには、ぜひ本文で、文例を読み込むことをお勧めします。
デジタル記事の書き方
・記事を説明文にせず、物語(ストーリー)にする
・出だしは、できれば場面の描写から入る
・リードの末尾には、本文に読み進んでもらうための「匂わせ」を入れる
・主人公を一人立てて、場面ごとに主人公の気持ち・感情を書き込む
・できれば時制をさかのぼらず、時系列で書く
・一文を短くし、テンポを良くする。主語の前に長い修飾を付けない
・カギカッコの前にはできるだけその発言者を置き、後ろに述語を置かないようにする
・接続詞や指示語をくどいくらい付け、段落や文同士の関係性を明確にする
・データや識者の言葉など「説明文」になりがちな要素はストーリーの後ろに回す
・新聞慣用の省略形は使わない
・表記に迷ったら、グーグルトレンドで比較する
また、著者も書いているように、この新しい書き方を実践するためには、これまで以上に綿密な取材が必要。
特に主人公を立ててストーリー仕立てにするには、情景描写に必要な当時の様子や当事者の言葉、時系列の確認が必要不可欠です。
書かれていることのほとんどは、実際に手を動かして覚える内容で、ベテランの書き手ほど、訓練を要する内容だと思いました。
ネットでバズる記事が書きたい、若者に共感してもらえる文章が書きたいと願う向きに、お勧めの内容です。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
読者の共感を得ようと思えば、記事に書かれている内容を読者に追体験してもらい、感情移入してもらいやすくするのが手っ取り早い。構成をストーリー仕立てにすることで、記事の登場人物に起きたことが、まるで読者自身が体験したことのように感じてもらえるようになる
具体的にどこが難しいのかを聞くと、3人とも共通していた。「最初の部分」この言葉を聞いて、率直に驚いた。彼らが言う「最初」とはつまり記事の冒頭部分だ。読んでもらった記事の冒頭には、重要な要素が簡潔にまとまった内容が入っている。新聞的な逆三角形スタイルだ。そのリードが、分かりにくいと言われている。まさか、と思った。そこで「何がどう分かりにくいのか、もう少し具体的に教えてほしい」と頼んだ。すると一人は、このように言語化してくれた。「なんていうか、初っぱなから情報量とか固有名詞が多すぎて、頭使わないといけないというか、疲れる」
「カギカッコの中が短ければまだいいけれど、カギカッコ内の発言が長いと、誰が何を言いたいのか分からないまま読まないといけないから、途中で読みたくなくなる。カギカッコを読み終わって、その後ろに発言者とか発言した意図とかが出てきて、そこでやっと『ああそういうことか』と分かるのはストレス。誰が何を言いたいのかを、カギカッコの後じゃなくて、前に置いてほしい」
カギカッコについては、ほかにこんな形が読みにくいという指摘も比較的多かった。
【例】「~と話した。」
つまり、単純に「カギカッコの後に述語が来るのが嫌」という意見だ
「日航」は読者にとってなじみのある表現だろうか。確かに「日航ホテル」という表現もあるにはあるが、一般には「JAL」のほうが慣れているのではないだろうか。そこで、グーグルトレンドを使って、ここ1年間で「日航」と「JAL」のどちらが頻出しているかを調べた。結果はJALのほうが圧倒的に多かったため、日航の表記をすべてJALに変えた
デジタル記事の書き方
・記事を説明文にせず、物語(ストーリー)にする
・出だしは、できれば場面の描写から入る
・リードの末尾には、本文に読み進んでもらうための「匂わせ」を入れる
・主人公を一人立てて、場面ごとに主人公の気持ち・感情を書き込む
・できれば時制をさかのぼらず、時系列で書く
・一文を短くし、テンポを良くする。主語の前に長い修飾を付けない
・カギカッコの前にはできるだけその発言者を置き、後ろに述語を置かないようにする
・接続詞や指示語をくどいくらい付け、段落や文同士の関係性を明確にする
・データや識者の言葉など「説明文」になりがちな要素はストーリーの後ろに回す
・新聞慣用の省略形は使わない
・表記に迷ったら、グーグルトレンドで比較する
実際に多く読まれた記事の見出しのパターン
(1)カギカッコ付きのパワーワード
(2)問いかけ
(3)他人の感情
(4)ストーリーの予告
—————————-
理解の早い方なら、135ページに書かれたデジタル記事の書き方のおさらいを読むだけでわかるかもしれませんが、本当に書けるようになるには、じっくり文例を読むことをおすすめしたい。
著者が新聞の書き方を熟知した方のため、何がどう違うのか、はっきり対比してわかる、良い内容です。
新聞、新聞系出版社上がりの人には、本当に衝撃的なことが書かれていますので、ぜひ読んでみてください。
また、読まれた記事の見出しのパターンについても、見出しの例をしっかり読み込んでもらうと理解が深まると思います。
ネットでウケる書き方の要点がわかる内容で、これはオールドメディア出身者は全員読んだ方がいいですね。
激推しの一冊です。
———————————————–
『新聞記者がネット記事をバズらせるために考えたこと』斉藤友彦・著 集英社
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4087213501
<Kindleで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0DWMPFV2F
———————————————–
◆目次◆
はじめに
第1章 新聞が「最も優れた書き方」と信じていた記者時代
第2章 新聞スタイルの限界
第3章 デジタル記事の書き方
第4章 説明文からストーリーへ
第5章 メディア離れが進むと社会はどうなる?
おわりに
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
同じカテゴリーで売れている書籍(Amazon.co.jp)
お知らせはまだありません。