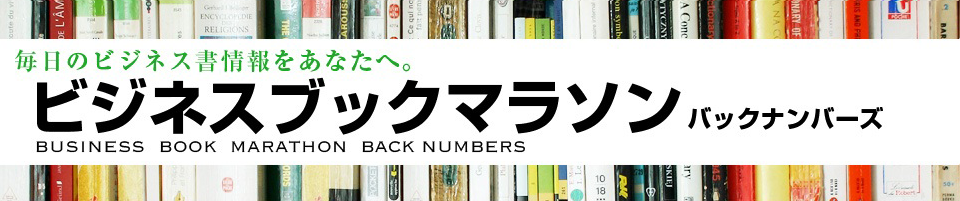【情報収集で大切なこと】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478120781
若い頃はインタビュアーを経験し、今はコンサルタントをしている経験から、成果って本当に質問で決まるなあと実感しています。
本日ご紹介する一冊は、<「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた>という、『「なぜ」と聞かない質問術』。
著者は、東京大学卒業後、国際協力コンサルタントとして活動し、現在は認定NPO法人ムラのミライ代表理事を務める中田豊一さんです。
本書でも指摘されている通り、「なぜ」と聞くと、人は事実ではなく「思い込み」を話してしまう。
そして悪いことに、「なぜ」は相手に言い訳を強要し、問い詰めることになってしまいます。
モラハラが問題になっている昨今、これは避けたい事態ですよね。
本書では、これらを避けるために、「事実質問」というメソッドを紹介しています。
事実のみに光を当てることで、「思い込み」「記憶違い」を排除し、事実を最速で正確に確認するやり方です。
第2章では、この事実質問の作り方を、第3章では、この事実質問の繋ぎ方を書いており、対話のなかでスムーズに問題発見・解決するやり方を紹介しています。
相手に詰問するやり方ではなく、事実を確認しているうちに悟ってもらう、真の問題点に気づく理想的な対話の手法が説かれており、これは一読に値します。
職場の上司はもちろん、コンサルタントやコーチ、教師などの職業に就いている方は、ぜひ読んでおくといいと思います。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
理由を直接尋ねても、真実は見えてこない
「なぜ?」は相手に言い訳を強要する
知識、情報、経験などに差があり、信頼関係が築かれていない場合、「なぜ質問」は力関係やモチベーションの差を強化するだけの危険な質問として機能する恐れがとても強い
よいコミュニケーションの出発点には、良い質問がある
「いつも」「普段は」あるいは「日本人は」「この会社の人たちは」などの「一般化した言い方」も、すべて同様に相手の思い込みを尋ねているにすぎません
「事実を淡々と積み重ねる」は、解釈を揃える唯一の方法
事実質問は、「答えが1つに絞られる質問」
5W1Hのうちの、WhyとHowを除いた疑問詞を使った質問は事実質問です。つまり、When「いつ」、What「何」、Where「どこ」、Who「誰が(誰と)」です
事実質問かどうかのチェック
1 Why・Howを使っていないか?
2 過去形、もしくは、現在進行形か?
3 主語が特定されているか?
事実質問の原則:「考えさせるな、思い出させろ」
「なぜ」と聞きたくなったら「いつ」と聞く
「なぜ?」と聞かずに「Yes/Noの過去形」に変える
「どう」と聞かずに「何」「いつ」
「どこ」「誰」と聞く
「いつもは」ではなく「今日は?」、「みんなは」ではなく「誰?」と聞く
次の質問に困ったら「他は?」と聞く
最初の質問は、いいところ、聞かれて心地よいところを見つけて、それについての事実質問から始める
「思い出すだけで正確に答えられる質問」をする
—————————-
「なぜ」と聞く習慣を改め、事実質問を繰り広げていくうちに、きっと会話が生産的になっていくはず。
そうすれば、画期的な問題発見、問題解決にもつながっていくはずです。
ぜひ、読んでみてください。
———————————————–
『「なぜ」と聞かない質問術』中田豊一・著 ダイヤモンド社
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478120781
<Kindleで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0DSGZKMCP
———————————————–
◆目次◆
プロローグ
序 章 よくない質問が「会話のねじれ」を生み出す
第1章 「事実質問」は最良の知的コミュニケーション
第2章 事実質問のつくり方 定義と公式
第3章 事実質問の繋ぎ方 始め方から終わり方まで
第4章 事実質問がすべて解決する
おわりに
この書評に関連度が高い書評
同じカテゴリーで売れている書籍(Amazon.co.jp)
お知らせはまだありません。