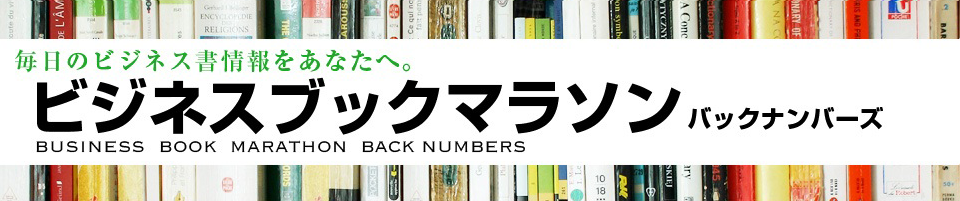【世界が見える、教養としての宗教論】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4121508319
本日ご紹介する一冊は、東京大学名誉教授、国際基督教大学名誉教授で、科学史家の村上陽一郎さんによる、教養としての宗教論。
世界的に分断が進む昨今、歴史や宗教を学ぶのは、ビジネスパーソンにとっても意味があることだと思います。
本書では、われわれの社会がいかに宗教の影響を受けているのか、それぞれの宗教がどんな考え方を持っているのか、なぜキリスト教圏で科学が発達したのか、科学の専門家である著者が、持論を述べています。
特に日本人が知らないギリシャ正教やイスラム教、ヒンドゥー教などの考え方が示されており、それぞれの宗教を信仰する国の根本的な思想がわかります。
科学に詳しい著者だけに、なぜ科学がキリスト教圏で発達したのかを説明した以下の部分は、特に読み応えがありました。
<『創世記』では、この世界は神によって「造られた」とされます。時計細工師によって造られた時計は、中を調べれば、細工師がどのような設計図の許に、作品を造ったかが鮮明に判ります。アリストテレスはその著『形而上学』(出隆訳、岩波文庫)の冒頭で、人間は生まれつき知ることを欲する、と明言しますが、そうした(宗教の立場に立てば「被造世界」)を知ろうとする、知れば知るほど、造物主としての神の設計図(よく<voluntas Dei>つまり「神の企図」と言われます)が、判って来る喜びを得られます>
最近の自己啓発書でも、「好奇心を持とう」などと言われますが、単なる掛け声だけで好奇心が湧いてくるはずはありません。
本書を読むと、日本人がなぜ宗教を怪しいものだと考えてしまうのか、なぜ勉強や仕事に本気になれないのか、その根本のところがよくわかります。(もちろん、人によりますが)
グローバルに仕事する人にとっては、先方の価値観を知る上でも、読んでおきたい一冊だと思います。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
宗教とは、単なる知識の世界を超えて、人間の知・情・意の全て、ひとことで言えば「魂」と直に切り結ぶことで成立する「信仰」という営みに関わるものです。しかし、もう一方では、宗教はそれぞれの文化圏の根本となるところを造り上げる役割を果たしており、そのことについての知的な理解なくして、文化の、あるいはその所産の一つとしての文芸の世界に接近することも不可能です
カレンダーの基礎を「週」と定め、一週間を七日とし、七日目を休日とする、というような生活習慣は、本来ユダヤ教に発したもの
ノア、アブラハム、モーセ、イエス、そしてムハンマドの五人は、イスラム世界では、預言者の中で別格の存在
「キリスト教圏」という意味では、現代ギリシャは、実は極めて重要なリーダーの一つであり、しかも、西欧的な規格から外れた
『創世記』では、この世界は神によって「造られた」とされます。時計細工師によって造られた時計は、中を調べれば、細工師がどのような設計図の許に、作品を造ったかが鮮明に判ります。アリストテレスはその著『形而上学』(出隆訳、岩波文庫)の冒頭で、人間は生まれつき知ることを欲する、と明言しますが、そうした(宗教の立場に立てば「被造世界」)を知ろうとする、知れば知るほど、造物主としての神の設計図(よく<voluntas Dei>つまり「神の企図」と言われます)が、判って来る喜びを得られます
日本語でも「生きる」と「息をする」とは、音韻ではほとんど同じで、同根であることが判りますが、そこから「生命」にも通じる使い方が生まれます。さらに、英語では、<inspire>(同じくラテン語の動詞<inspirare>と同じ)つまり「息を吹き込む」にも繋がります
<fact>とは本来<what is done>、つまり「人間によってなされた何事か」を指す言葉
人類は、食欲、性欲、征服欲など、哺乳動物にも備わっている本能的な欲求を、同じく本能の中に仕込まれている、それらの過度の使用への禁忌という、他の動物が備える仕組みを破壊したかに見える、人間の本性に対して、宗教という社会的な権威に発する抑制装置によって、対応してきた
ギリシャ語(ローマ字化しておきます)の<katholikos>の意味は、「全体の」「普遍的な」で、英語に直せば<universal>が原意ということになります。「全人類に遍く」という意味を伝えています
—————————-
世界が分断に向かう今、厳格だと思われがちなカトリシズムがある程度の柔軟性を持っていたからこそ二千年生き残ったとする解釈が面白い。
頑なだと、自らが壊れるか相手を破壊するかしかないので、この解釈は、世界平和につながる考え方でいいですね。
ちょっとした雑学として、また複雑な世界を紐解くヒントとして、ぜひ、読んでみてください。
———————————————–
『科学史家の宗教論ノート』村上陽一郎・著 中央公論新社
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4121508319
<Kindleで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0DRJ819PF
———————————————–
◆目次◆
まえがき
序 章 教養としての宗教
第1章 宗教と科学
第2章 宗教の起源
第3章 スピリチュアルとオカルティズム
第4章 欲望と禁忌をめぐって
第5章 聖書とは何か
第6章 アジア大陸の聖典
第7章 国家と宗教
第8章 無神論・反神論
第9章 科学的合理性と宗教
終 章 信仰と私
あとがき
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
同じカテゴリーで売れている書籍(Amazon.co.jp)
お知らせはまだありません。