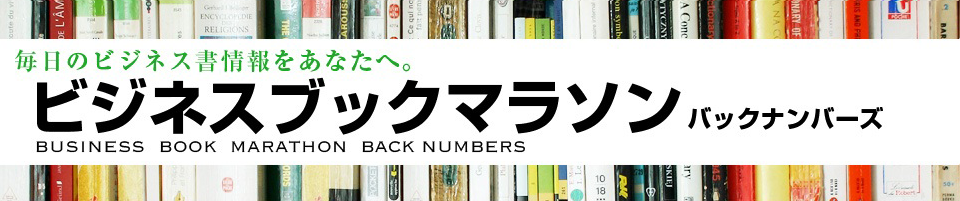【注目の新出版社から第1弾】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799331175
本日ご紹介する一冊は、KADOKAWA(中経出版)、ダイヤモンド社で経験を積んだ藤田悠さんが立ち上げた、新しい出版社「テオリア」の第1弾。
タイトル通り、新時代の『冒険する組織のつくりかた』を指南した一冊です。
著者の安斎勇樹さんは、経営コンサルティングファーム「MIMIGURI(ミミグリ)」の創業者で、同社は資生堂、シチズン、京セラ、三菱電機、キッコーマン、竹中工務店、東急などの大企業のほか、マネーフォワード、SmartHR、LayerX、ANYCOLORなどの注目のベンチャー企業をクライアントとしています。
これまでに合計350社以上の組織づくりを支援してきた経験から、これからの時代の組織づくりの法則を説いており、「冒険する組織をつくる『5つの基本原則』」、「新時代の組織をつくる『20のカギ』」などを記しています。
立教大学経営学部教授の中原淳さん、文芸評論家の三宅香帆さんが推薦しており、新会社立ち上げへの意気込みが感じられる一冊です。
450ページ近い分厚い本ですが、読みやすいレイアウトと中身で、サクサク読み進められると思います。
「軍事的世界観」を抜け出し、ワクワクするチームをつくるための「世界観を変える5つのレンズ」は、これから自社をどう変えていけばいいか、良いヒントとなるに違いありません。
■世界観を変える5つのレンズ
(1)目標のレンズ 行動を縛り上げる指令→好奇心をかき立てる問い
(2)チームのレンズ 機能別に編成した小隊→個性を活かし合う仲間
(3)会議のレンズ 伝令と意思決定の場→対話と価値創造の場
(4)成長のレンズ 望ましいスキル・行動の習得→新たなアイデンティティの探究
(5)組織のレンズ 事業戦略のための手段→人と事業の可能性を広げる土壌
また、目標設定の新法則「ALIVE」も、チームが前に進むための推進力になると思います。
■目標設定の新法則「ALIVE」
・Adaptive--変化に適応できる
・Learningful-学びの機会になる
・Interesting-好奇心をそそる
・Visionary-未来を見据える
・Experimental-実験的である
リーダーが本書を読んで終わるのではなく、経営幹部やメンバーと話し合い、組織づくりに取り組むことによって、自社の新しい目標や方向性が見つかる、そんな本だと思います。
さっそく、本文の中から気になる部分を赤ペンチェックしてみましょう。
—————————-
■冒険する組織をつくる「5つの基本原則」
(1)目標の基本原則
-目標は新法則「ALIVE」で設定する
(2)チームの基本原則
-マネジメントチームは組織の靭帯
(3)会議の基本原則
-ハレとケの場づくりに工夫を凝らす
(4)成長の基本原則
-学び続ける組織文化を醸成する
(5)組織の基本原則
-毎日が変革! 変えることを楽しむ
ミドルマネジャー同士を“横”につなぐチームの形成
組織文化を醸成するためには、「暗黙の前提」レベル、つまり、明確に言葉になっているわけではないにせよ、いつのまにかみんなの行動を左右している規範に働きかけなくてはなりません
現場の目標にこそ「追いかけたくなる意味」を込める
そもそも、私たちの顧客にとっての『真の成功体験』とは、いったいどんなものなんでしょう?
冒険する組織における経営理念は、「みんなで冒険する理由」そのもの
「事前のヒアリング」と「事後のストーリーテリング」で、目標設定はうまくいく
■自己紹介で精神的なつながりをつくる、
「感情にフォーカスした語り」
・もともとどんなことが好きで、なにをやりたかったのか
・いまの仕事に就くときに持っていた想い
・現在、モチベーションに感じていること
・将来的に挑戦したいなと思っていること
・楽しいと感じること
・不安や葛藤を感じていること
・苦手だ、嫌いだと感じていること
■チームのアイデンティティを言語化する3つのコツ
・連想ゲームを用いたチームアイデンティティの言語化
・チームに名前をつける
・チームの経営理念をつくる(ローカル理念)
■チームのアイデンティティを生成する2つのコツ
・独自ルーティン
・メンバー巻き込み型採用
■チーム内の問題が見つかる「KMQT」リフレクション
・Keep-印象に残っているよかったこと、これからも続けたいこと
・Moyamoya-プロジェクト活動のなかでなんとなく引っかかっていて気になること、“モヤモヤ”すること
・Question-向き合っていきたい問い、探究していきたいこと(“モヤモヤ”を問いに変換すると?)
・Try-今後やってみたいこと
冒険型ナレッジマネジメントのコツ
(1)形式知は「使いやすく編集」して現場に届ける
(2)「社内メディア」を活用して流通させる
(3)「葛藤や失敗談」もナレッジとして尊重する
—————————-
原理原則だけではイメージが湧かない、という人は、著者の会社が手掛けた、「冒険する組織づくり」の事例、あるいは著者自身の会社の事例を読めば、具体的なところがわかると思います。
人手不足の苦難を超えて、優秀で前向きな人材が集まる組織をつくるために、ぜひ読んでおきたい一冊です。
———————————————–
『冒険する組織のつくりかた』安斎勇樹・著 テオリア
<Amazon.co.jpで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4799331175
<Kindleで購入する>
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0DTJYRFZ3
———————————————–
◆目次◆
はじめに
序論 “冒険する組織”とはなにか?
第I部 理論編 冒険する組織の考え方
第1章 会社の「世界観」を変える
第2章 自己実現をあきらめない「冒険の羅針盤」
第3章 冒険する組織をつくる「5つの基本原則」
第II部 実践編 新時代の組織をつくる「20のカギ」
第4章 冒険する「目標設定」のカギ
第5章 冒険する「チームづくり」のカギ
第6章 冒険する「対話の場づくり」のカギ
第7章 冒険する「学習文化づくり」のカギ
第8章 冒険する「組織変革」のカギ
おわりに
注
この書評に関連度が高い書評
この書籍に関するTwitterでのコメント
同じカテゴリーで売れている書籍(Amazon.co.jp)
お知らせはまだありません。